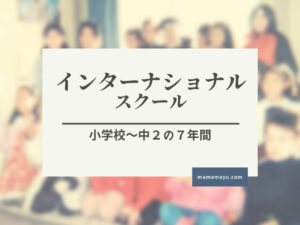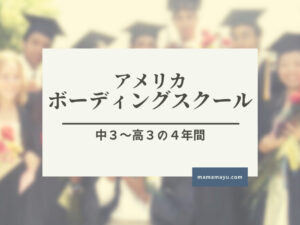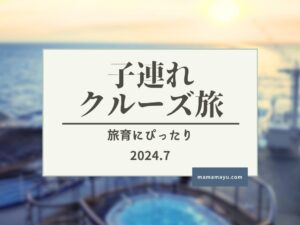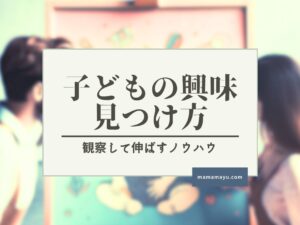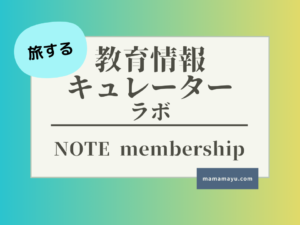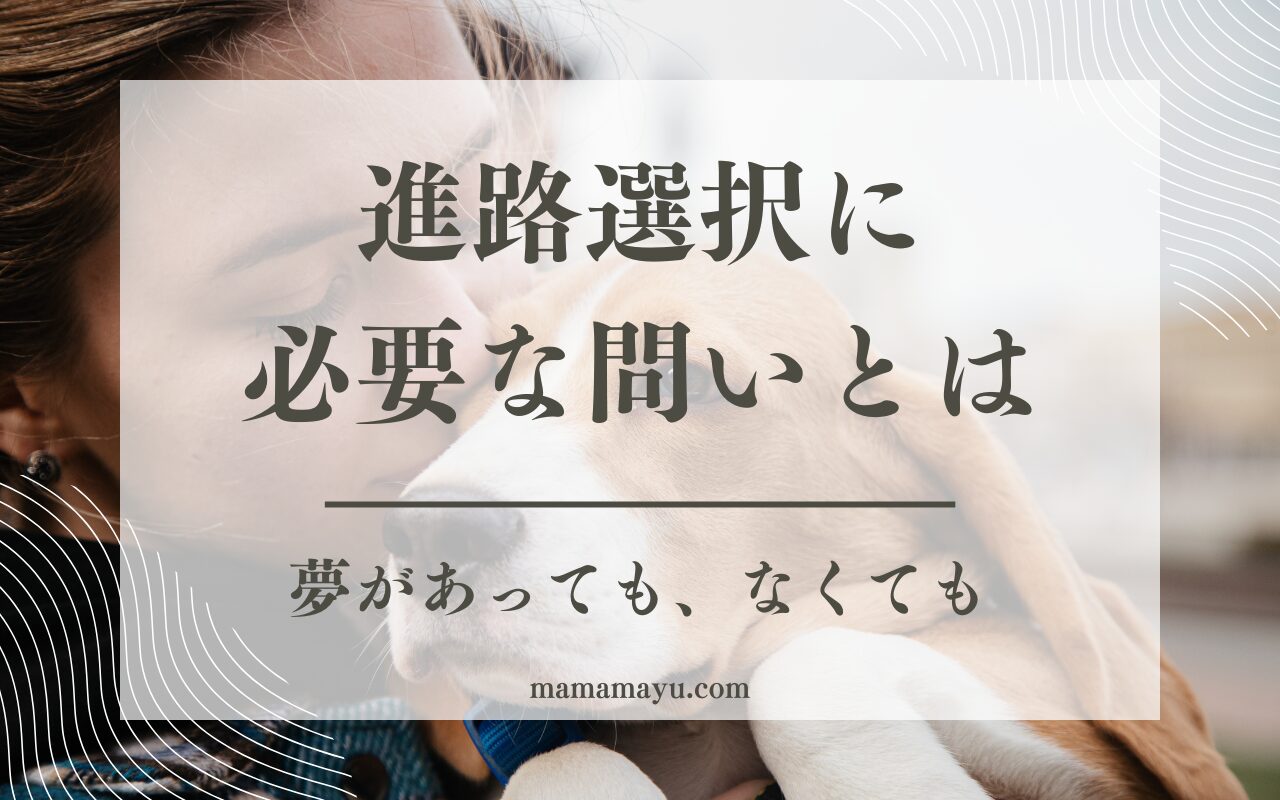進路や子どもの夢の相談を受けていると、本当にいろんなタイプの子や親御さんに出会います。
昔から一つの夢を追い続けている子もいれば、なかなか「これ!」と決められない子もいる。
決まったと思ったら、次に会うときには別のことを言っている。
「あれもこれもやってみたい」「まだわからない」と迷う子もたくさんいます。
どのタイプも、そのままで十分に素敵です。
そんな中、「獣医を目指している」という相談者さんのお話を聞く機会がありました。
私はペットを飼ったこともないし、この分野はまったくの素人です。
でも「知らないこと」「わからない世界」のほうが、相談をもらえるとワクワクしながら調べるタイプ。
知らないテーマに触れるたび、他の知識ともつながるのがとても楽しいんですよね。
たくさんの情報や価値観に日常的に触れることは、進路や夢と向き合ううえでもめちゃくちゃ大切です。
そんなリサーチのなか出会ったのが、今回ご紹介したいコーネル大学獣医学部の公式YouTube動画でした。
コーネル大学獣医学部が提唱する「スペクトラム・オブ・ケア」
コーネル大学というと、アメリカにある獣医学の分野では世界トップレベルの大学です。
そんな一流の獣医養成機関が、「獣医と飼い主とペットが全員納得できる治療選択とコミュニケーション」のグッドプラクティスを紹介していました。
題名にある「Spectrum of Care(意訳:幅広い診療)」という言葉を目にして、私はなんとなく医療現場でいろいろな選択肢を出してくれるやつかな?くらいの軽い気持ちで見始めたんですけど、ちょっと驚かされました。
動画のなかでは、
「治療にも色んな選択肢があります」
「全部やれば正解、ってわけじゃなく、今の家族の状況や気持ちも一緒に考えていきましょう」
「わからないことは遠慮なく聞いてほしい」
そんな風に、獣医さんと飼い主さんが一緒に悩みながら答えを探していく様子が描かれていました。
これって…いわゆる「インフォームドコンセント(=きちんと説明して納得してもらうこと)」ですよね。
この「プロに選択肢を出してもらえる」「些細なサインを見落とさずに、否定せずに、一緒に考えてもらえる」って、難しいですが医療やサービスではすでに当たり前に目指しているところだと思っていました。
営業経験があったり、医療を受診をしたことがある私にとっては当たり前のことだと思っていた「インフォームドコンセント」ですが、
でもコーネル大学獣医学部が最近もこの動画をアップしているということは、きっとまだ業界スタンダードではないということなのでしょうか。
また、ペット自身が治療を決める主体にはなれない分、飼い主や獣医の「説明する・聴く」力が、人間の医療以上に試されるんだろうなと、動画を見ながら改めて実感しました。
コーネル大学獣医学部が提唱する「スペクトラム・オブ・ケア」をもっと知りたいかたは、動画をご確認ください。
日本のペット医療現場の現状
では実際、日本のペット医療現場ってどうなんだろう?
ちょっと調べてみるとそこそこ出てきました。
治療費や方針の説明不足、思い込みや情報の非対称性が原因で、
・診療トラブルや誤解
・費用をめぐるクレームや裁判
・信頼して預けたのに説明がなかったという不満
が存在していること。
「ちゃんと説明してほしかった」と感じる飼い主さんもいれば、「専門家が言うなら…」と遠慮して質問できないまま後悔した人も多いそうです。
これって、普段から「子どものために何ができるか」を考えている保護者として見たら、すごく気になる現実です。
説明不足や経済的な理由で必要な医療を受けさせられなくて、大事なペットの治療を受けない。またはペット自体を手放してしまう。
精神的・経営的負担による獣医師の離職と人材不足。
こうした問題は、ペットと人間がお互いに幸せに暮らす「共生」の理想から遠ざかる要因になると、ペットを飼ったことがない私でも想像できます。
私の考える「共生」とは、ペットの飼い主や獣医療従事者だけでなく、ペットを飼わない人にとっても過ごしやすい社会のことです。
ペットや飼い主や獣医療従事者が不幸であっては、よろしくない。
だからこそ、「スペクトラム・オブ・ケア」のような多様な選択肢提示・対話型アプローチが「飼い主・ペット・獣医の三方良し」に必要だと思います。
獣医学教育の現場でも最近は「医療コミュニケーション」「情報共有・合意形成力」を扱う科目が増えてきているという話も聞き、現場がまだ追いついていなくても、少しずつ変わってきている空気は感じます。
ちなみに普段からいろんな出来事や意見に触れていると、業界の変化にも気づきやすくなります。
「どんな獣医になりたい?」という問いの重要性
ここまで調べて私が強く思ったのは「獣医になりたい」って宣言すること自体ももちろん素敵なんですが、「どんな獣医になりたいか」を問い続けることも大事ということです。
獣医として働こうとする子どもたちに必要なのは「困っている人や動物にどんな風に向き合いたい?」と、自分ごととして考え続けられる姿勢だと思うのです。
技術や知識だけではなく、「どうありたいか」。
これはどんな職業や大人になっても問われることだと思います。
そして近年では、海外でも国内でも「どうありたいか」「そのために何をしてきたか」をエピソードで語れるひとがますます評価される時代になってきていると感じます。
すぐに答えが見つからなくても、もちろん大丈夫です。
まとめ
今回は、獣医を目指す子を支えたいというご相談から、私が調べて気付いたプロセスを共有しました。
進路も夢も、正解もスピード感も人それぞれです。
「自分はなぜこれをしたいんだっけ」「どういう人・どういう社会を目指したい?」という本質的な問いを小さいうちから何度も問い直していくことは、確実に未来への資産になります。
親としては、「早く決めてほしい」「ブレないでほしい」と思ってしまうこともあるかもしれませんが、
親が子どもの歩みを邪魔せずにできることがあるとしたら、
子どもの迷いに耳を傾けて、ときには一緒に感じて考えたり、「そのままのペースでいいよ」と声をかけることです。
あとは、普段から様々な情報源や考え方に一緒に触れることでしょうか。
親子でぜひ「わたしらしい獣医像」「これからなりたい大人像」「理想の社会のあり方」について、今日からまた話してみてくださいね。