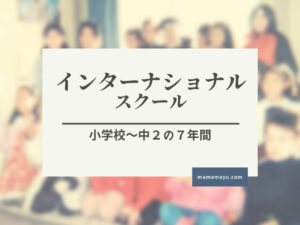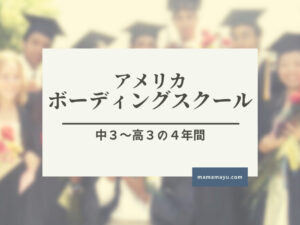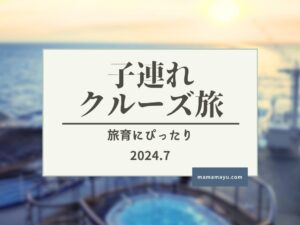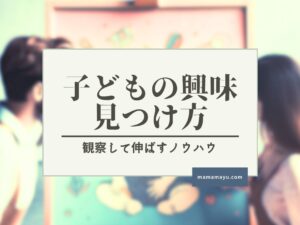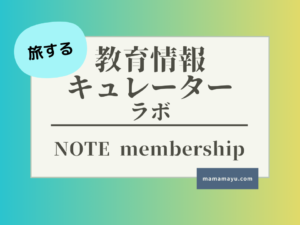子どもの個性や才能を伸ばしたい。
でも情報があふれる中で何を信じ、どう実践すればいいのか悩む。
そのような保護者の方は多いのではないでしょうか。
この記事では、全12回の教育セミナー「君が志望校を決める前に、お金と仕事の話をしよう。教育乱世を幸せに生き抜く親子セミナー」の第2回で私が語った「親の情報力」についてお伝えします。
- 子どもの個性や可能性を見つけ出す「いいお顔」の観察法
- 教育情報の集め方・活かし方、7つのステップ
- セミナーの参加者・主催者の生の声と実践のヒント
セミナーシリーズの全体像
「君が志望校を決める前に、お金と仕事の話をしよう。教育乱世を幸せに生き抜く親子セミナー」は、2025年4月〜7月に全12回開催される無料オンラインセミナーシリーズです。

対象は10〜16歳の子どもとその保護者。
各界の専門家12名が「幸せに生きる力」をテーマに、進路・教育・お金・仕事について多角的に語ります。
従来のいわゆる「偏差値・学歴重視」から、「なりたい自分」「目指す幸せ」から逆算して教育を選ぶ。
そんな新しい羅針盤を親子で手に入れることを目指している画期的なシリーズです。
「親の情報力」で子どもの個性を伸ばす方法|登壇内容まとめ
私は、全12回のオンラインセミナーシリーズの第2回「教育情報の上手な集め方・活かし方:子どもの可能性を広げる親の情報力とは」を担当しました。
2025年4月27日(日)の20時から、オンラインで開催しました。
情報があふれる現代で、親がどのようにして子どもの個性や可能性を引き出す情報を集め、活かせるのか。
その具体的な方法と考え方についてお話ししました。
かいつまんで、ご紹介します。
親の情報力を高める7つのステップ【全体像】
セミナーでは、子どもの個性や可能性を伸ばすために親が意識したい情報収集と活用の流れを7つのステップでまとめました。
全体像がこちら。
- 観察する
- 仮説を立てる
- 情報を集める
- 整理・選択する
- 試してみる
- 振り返る
- 共有する
この流れを意識することで、子どもの個性や可能性を伸ばすヒントが得られます。
それぞれのステップを具体例は、記事の後半にて解説します。
日々の観察や声かけで子どもの興味を伸ばすコツは、「子どもの興味を伸ばすヒント」でも書いています。あわせてご覧ください。
子どもの「いいお顔」とは?個性と可能性を見つけるサイン
セミナーでは、子どもの「いいお顔」をキーワードにしていました。
「いいお顔」とは、子どもが心から楽しんでいる時や夢中になっている時に見せる、その子らしい自然な表情です。
たとえば:
- 何かに熱中して目が輝いている瞬間
- 新しいことができた時の誇らしげな表情
- 自分の興味があることを話す時の生き生きとした様子
- 困難を乗り越えた時の充実感に満ちた表情
こうした表情は、その子の本来の興味や才能、可能性を示すサインとなります。
ポイントは、親や周囲の期待に応えようとする「作られた笑顔」ではなく、子ども自身の内側から自然とあふれる表情であることです。
子どもの個性をもっと深く知りたい方は、「個性を認める子育て」も参考にしてみてください。家庭でできる工夫やヒントをまとめています。
子どもが自分で幸せをつくる力を育てるには
「いいお顔を再現できるようになること」は、ただ親が子どもの笑顔を引き出すだけの話ではありません。
本当に目指したいのは、いずれ子ども自身が「自分のいいお顔」をつくり出せるようになることです。
親が観察し、環境や体験を用意し、気付きを言語化することで、子どもは「自分はこんな時に幸せを感じる」「こういうやり方が好き」と少しずつ気づいていきます。
この気づきが、自分で自分の幸せをつくる力、つまり自立の土台になります。
子ども自身の気づきと自立につなげる
繰り返しになりますが、大切なのは、親が一方的に「こうすればいい」と決めつけるのではなく、子ども自身が「自分はこうした時に心地よい」「このやり方が好き」と感じる力を育てること。
そのためには、子どもが自分の気持ちや特性に気づけるよう、日々の会話や体験を通じてサポートし続けることです。
この「いいお顔を自分で再現できる力」は、子どもが自分で自分を幸せにする力につながります。
たとえば、学校や友達との関係でつまずいた時も、「自分はどんな時に元気が出るのか」「どうすれば自分らしくいられるのか」を考え、自分で立ち直る方法を身につける助けになります。
進学や転職など人生の大きな選択をする場面で、「自分はどんな時にワクワクするか」「どんな環境が合っているか」を考え、自分の価値観で道を選ぶことができます。
他人の意見や世間の常識に流されず、「自分はこれが好き」「これをやってみたい」と感じる気持ちを大切にすることで、自分だけの生き方を切り拓いていけます。
仕事で失敗したり、人間関係がうまくいかず落ち込んだりしても、「自分はこうすれば前向きになれる」と理解していると、周囲に流されず自分らしさを保ちやすくなります。
自分の特性や好きなことを理解し、自分で選び、工夫し、幸せをつくり出せる人になる。
そんなことが当たり前だと感じられる人が一人でも増えてくれたら、生きやすい世の中に近づくのではないかと思っています。
その土台を、親子の対話や日々の観察から育んでいきたいと考えています。
もし「うちの子はまだ自分で気づけないかも」と感じる時は、まずは子どもの様子をそっと観察するところから始めましょう。
子どもが自分の”いいお顔”を自分で見つけられる日を、ゆっくり待ちながらサポートしていきましょう。
「親の情報力」セミナー参加者・主催者のリアルな声
このセミナーに関わってくださったみなさまからいただいた感想や気づきをご紹介します。
主催者コメント
主催者のひとりである、リアル孟母ベティさんのコメントをご紹介します。
親が子どものために情報を集めてくれば子どもの人生をこんな風に変えられるっていうお話も出るかと思っていたんですけれどね。
萩原先生にそんな視点はほとんどなく、本当に自然にありのままの子どもを観察して、その子が伸びたい方向に伸ばしてあげましょう!そのためにあるのが情報です!というお話をしてくださったんですよね。
情報もただ集めればいいというものではなく、子どもに向いたものはなんなのかという仮説にそって集めるべきということをお聞きして、私は、これは親はエゴとの闘いだな!と思いましたよ。
だって、ちょっと手を加えて、こっちの方に行かせたいなーっていうの、絶対親なら思っちゃうじゃないですか。
どうやって自分のエゴやバイアスをステップ2に入れないでおけるか。
ただありのままに子どもを見てあげられるか。萩原先生はこのために教育コンサルタントというお仕事をされているのかもしれません。
そして自分が発信者になることで、また情報が深くなり、広くなり、発展していくんだよ!っていう視点は新鮮でしたね。
情報発信者ならではの体験を通したご意見だと思います。
で、ここまでの7つのステップを、ずーっとつきっきりで観察して、集めて、試して、なんで出来るかっていうと、それは親の愛だな!と。
こんな風に関心を持ち、手を差し出していけばいい。
それがわかっただけでも、肩の荷がおりますよね。
これ全部「愛」! 親の情報力を要約すれば
参加者アンケート
参加者さんの事後アンケートからも一部抜粋します。
「いいおかお」を育むステップの話が参考になりました
トライ&エラーの繰り返し、子供の「いいおかお」再現性、子供自身に決めさせてその結果を背負わせるその積み重ねが大切という部分が胸に響きました。
育児をしていると迷いや決断する場面が沢山ありますが、一つ一つの心強いお言葉が背中をおして頂けているような気持になりました。先生のお人柄もとても素敵でした。
分かりやすく、即実践にうつせるような内容で充実したセミナーを有難うございました。
万人に当てはまる最適解はなく、むしろ世間受けする逆方向が合っている場合もあり、子供に合った道を探し導いてあげる事が大事なのだな、と思いました。
情報力とは集めるだけでなく活かす力も含まれる。具体的にはどういう事をすべきか、という事が聞ける大変勉強になるセミナー。
皆さま、ご感想をいただきありがとうございます!
もっと体系的に学びたい方へKindle出版のご案内
今回ご紹介した親の情報力の考え方や7つのステップは、その後Kindle書籍として電子出版されました。
迷ったときにすぐに調べられるように持っていたい方におすすめです。
Kindle書籍『教育情報の上手な集め方・活かし方:子どもの可能性を広げる親の情報力とは 【NEXT2035】 (NEXT2035 BOOKS)』
Kindle化のお知らせと内容については、こちらの記事にまとめています。
セミナー見逃し配信(アーカイブ動画)と見どころ
当日のセミナーはアーカイブ動画でご視聴いただけます。
アーカイブ動画の目次・チャプター紹介
アーカイブ動画自体は1時間以上あって長いので、主要なタイムスタンプを載せておきます。
第1部:プレゼンテーション
私からの”レクチャー”は、30分弱。ここにぎゅっと言いたいことを凝縮させました。
- 本編開始(00:07:28~)
- なぜ情報収集と活用をしたほうがいいのか(00:15:05~)
- 情報収集・活用の7ステップ解説(00:16:00〜)
- 私の経歴と情報発信をしている理由(00:30:15~)
- 結局、親の情報力とは(00:32:10~)
第2部:Q&A
後半は、ご質問にお答えしました。
- 情報を集めてばかりで「決める」のが苦手な場合、どうすれば良い?(00:37:10~)
- 観察→仮説→リサーチ→選ぶ。子どものいいお顔を再現する仮説を立て、安・近・短で絞り、小さく試し、反応を見る。
- 子どもにあえてコンフォートゾーン外の経験をさせた方がいい?(00:43:50~)
- 年齢・個性による。本人がやりたいならOK。無理させず観察し、トラウマになる経験は避ける。
- 学校が「つまらない」と感じている子にどうする?(00:46:15~)
- 学校外の時間充実を。動画・オンライン講座・見学・発信などで可能性を広げてみる。
- 「ゲームやサッカーしか興味がない」子でも、親はどう「好き」や可能性を見つけていけばいい?(00:50:58~)
- それが「いいお顔」ならOK。その中で深堀りやバリエーション、周囲の事例にも目を向ける。
- (萩原が)アメリカの大学を中退し日本の大学に転学した理由は?(00:53:04~)
- 高校でアメリカを充分経験したので、自由な学生生活求めて日本へ。結果自分に合っていた。
- (萩原の)ボーディングスクール進学は自分の意思?親の導き?(00:54:44~)
- 親の導きで決定。
- ハーフで英語環境、お友達大好きな子。アドバンテージを活かせていない気がする。どうしたら?(00:55:14~)
- 子ども本人がどう感じているかが重要。属性ではなく、いいお顔を観察して「合うフィールド」を探す。
- 内向的で思慮深い子でも、リーダーシップや外交性が必要では?(00:57:55~)
- フィールド次第。合う場所で力を発揮できれば良い。時間をかけ慌てず見つけていくことでOK。
- 親が自分の理解できないこと(ゲーム等)に子が熱中する時、どう理解・許容したら良い?(1:00:17~)
- 親がわからなくても、他の大人や事例、本・動画等で理解に努め、子どもの世界観を尊重する。
- 夏休みの体験やサマープログラムをお金をかけずに探す方法は?(1:07:28~)
- 複数の居場所や選択肢を作り、子ども自身にもリサーチ・判断させる。行政・市民団体・企業等も活用。
- 「子供に決めさせる」習慣をどう作ればいい?(1:10:03~)
- 小さなことから自分で決めさせていく。少しずつ判断を任せていき、最終的に大きな決断ができるように。
- 「母親の自己否定」が子供の成長を妨げるケースにはどう対応する?(1:14:04~)
- 多様な大人に出会わせる。親以外のロールモデルを増やし自己肯定感や視野を広げる。
こうして振り返ると、たくさんのご質問にお答えできていてよかったです!
家庭でできる「親の情報力」7つのステップ【実践例】
動画の内容のおさらいになりますが、親の情報力は「子どもで始まり、子どもで終わる」、これに尽きます。
日々の生活の中で子どもの姿をしっかりと見つめ、その子らしさを大切にすることから全てが始まります。
ここからは、7つのステップを実際に家庭でどう活かせるか、私自身の体験や身近なエピソードを交えて解説します。
1. 観察する
子どもの何を観察するか聞かれたら、私は一言で答えます。
それは「子どものいいお顔」です。
先入観を持たずに、子どもが自然と笑顔になる瞬間や、夢中になって取り組む様子を見つめることから始めましょう。
例えば、私の長男は工作やテニスに没頭する時間が多く見られます。
そんな彼の「いいお顔」を、日々の何気ない場面から読み取るように心がけています。
日々の観察や声かけで子どもの興味を伸ばすコツは、「子どもの興味を伸ばすヒント」でも詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
2. 仮説を立てる
次に、子どもの「いいお顔」を見せた瞬間に注目し、どんな環境や体験がその表情を引き出したのか考えます。
長男の場合、細かい作業に没頭している時や、テニスの試合を見ているときに特にいいお顔を見せます。
親が「こんな時にいいお顔になるのかな?」と仮説を立てることで、子どもの成長を支える次の行動が見えてきます。
3. 情報を集める
子どもの「いいお顔」が見られた場面を再現できそうな機会を探します。
オンラインや書籍で関連する活動を調べたり、地域の体験教室を探したりします。
子どもの興味に詳しい先生や専門家に相談するのも効果的です。
例えば、テニスに夢中な子どもなら、レベルに合った教室や、参考になる動画、家でも楽しめる練習方法を探してみるなどです。
4. 整理・選択する
集めた情報は、家族で話し合いながら整理します。
その際、比較検討することで思考を深めることができます。
ただし、最初から全てを試す必要はありません。
選ぶ時は「安・近・短(単)」がキーワードです:
- 安い、安心、安全なもの
- 物理的に近い、心理的に身近なもの
- 短期、短時間、単発で取り組めるもの
このような、子どもも保護者も取り組みやすい活動から始めることで、自然と次のステップに進めます。
「安・近・短(単)」でリスクが最小限のもののなかから、子どもが「やってみたい」と感じるものを一緒に選びましょう。
5. 試してみる
選んだ活動を実際に体験してみましょう。
子どもと一緒にイベントや体験教室に参加して、仮説通りの「いいお顔」が見られるか観察します。
たとえ最初はうまくいかなくても、それも大切な気づきになります。
「一緒にやってみよう」「失敗しても問題ない」という親の後押しが、子どもの挑戦する勇気を引き出します。
6. 振り返る
体験のあと、「どうだった?」と親子で感想を話し合います。
この振り返りは重要です。
仮説通りの「いいお顔」が見られた場合は、それが偶然なのか、再現性があるのかを確認するため、同じような体験を重ねてみましょう。
もし予想と異なる反応だった場合は、仮説を見直したり、別の角度から試してみたりすることで新たな発見につながります。
ときには観察からやり直すことも必要です。
このように「親の情報力」は常に子どもの様子を起点とし、子どもの反応で次の一手を決めていきます。
最初からうまくは行きません。やればやるほど勘が磨かれていくものです。
7. 共有する
最後に、得た経験や情報を家族や友人、SNSなどで発信していきましょう。
情報力は集めて活用するだけでなく、共有してこそ完結します。
誰かと共有することで子ども自身の学びが深まるだけでなく、みんなで育て合える情報の輪が広がっていきます。
良い経験は独り占めするものではなく、共に成長していくための贈り物なのです。
今後のご案内とサポートのご紹介
さらに深く学びたい方のために、相談窓口や最新情報の受け取り方法をご案内します。
サポートやコラボのご相談もお気軽にご利用ください。
保護者の皆さまへ
教育・出版・イベント関係者の皆さまへ
親の情報力で子どもを応援しよう
この記事では、親の情報力を高めることで、子どもの個性や可能性を引き出す具体的なステップや実践例を紹介してきました。
情報があふれる時代だからこそ、質の高い情報を見極め、子ども一人ひとりの「いいお顔」を大切にすることが、子どもの育ちの土台になります。
親が観察し、対話し、子ども自身が「自分らしい幸せ」を見つけられるようサポートすることは、将来の進路や生き方を選ぶ力につながります。
進路や職業だけでなく、ワークライフバランスや学び続ける環境、社会との関わり方など、子どもが自分の価値観を大事にしていけるようになってほしいですね。
迷いや不安があっても、親子で対話を重ね、時には他の家庭や専門家の知見も取り入れながら、「わが家らしい選択」を見つけていきましょう。
この記事が、その一歩を踏み出すきっかけや、日々の子育てのヒントになれば嬉しいです。
もし悩んだときは、ニュースレター登録や個別相談、イベント・セミナーへの参加もご活用ください。
親の情報力で、子どもの未来を一緒に応援していきましょう。
\他にもいろいろ書いています/