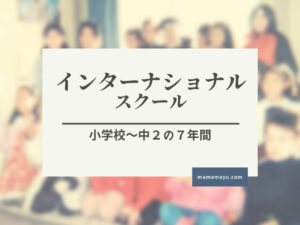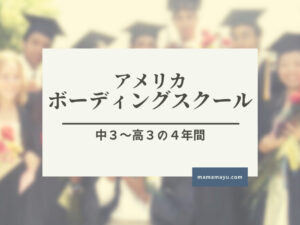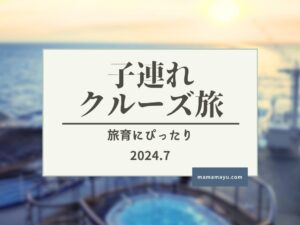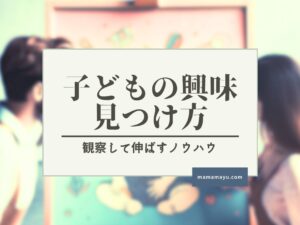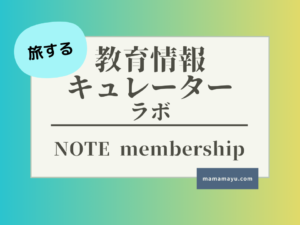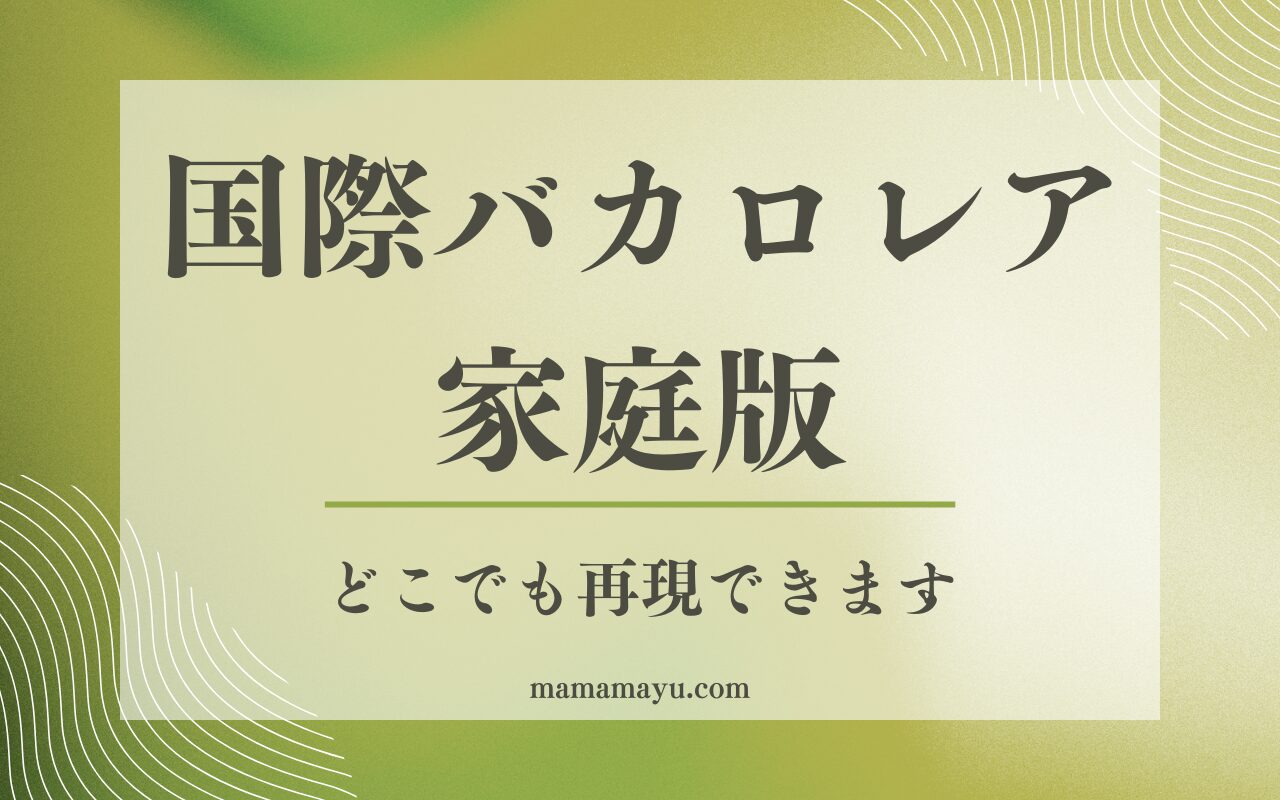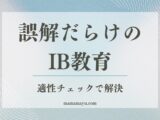前編の記事で国際バカロレア(IB)について詳しく解説しましたが、「うちの子には合わないかも」と感じた方もいらっしゃるかもしれません。
私は小6と小4の息子を「これでいいのかな?」と悩みながら日々子育てをしていく中で、ふと気づいたことがあります。
子どもたちの成長を願って続けてきた家庭での取り組みが、気がつくとIBの理念と似ている部分があるのではないかということです。
意図的にIBを真似したわけではなく、子どもたちを見ていて「これが必要かな」と思ったことを試行錯誤しながら続けてきた結果です。
これは特別なことではないのかもしれません。
子どもの成長を真剣に考える保護者なら、自然と似たようなアプローチにたどり着くこともあるのではないでしょうか。
今でこそ教育コンサルタントとして活動している私ですが、それ以上に一人の親として実感しているのは、IBの教育要素の一部は、特別な学校でなくても家庭の工夫で取り入れられる部分があるということです。
今回は、家庭でできる具体的な方法をまとめてみます。
あくまで選択肢の一つとして、参考になる部分があれば嬉しく思います。
家庭でIBの良いとこ取りをする方法
私がIBを見ていて圧倒されるのは、理念に向けた構造化の徹底ぶりです。
探究型学習、CAS、多面的評価、国際的視野といったIB独特の教育要素が、明確な理念のもとに体系的に組み立てられています。
ただし、これらの個々の要素は、特別な学校やプログラムでなくても、家庭の工夫で取り入れることが可能ではないかとも思います。
以下、IBの4つの特徴的な教育要素について、家庭での実現方法をまとめてみました。
1. IBの探究型学習を家庭で育む方法
IBの探究型学習は、「なぜそう言えるのか?」を問い続ける姿勢を重視します。
これは単なる知識の暗記ではなく、自分で問いを立てて調べ、考え、表現する一連のプロセスを通じて、知識を活用し創造する力を育む学習方法です。
家庭でできる具体的な実践方法
探究型学習の本質は「子ども主体の学び」にあると、私は思います。
それは本来、特別な教材や環境がなくても、日常の中で子どもの好奇心を大切にし、周りのひとと一緒に疑問を解決していく姿勢があれば育つものです。
重要なのは、大人が「教える」のではなく、子どもと一緒に「探る」ことだと考えています。
子どもの興味を起点とした探究
- 日常の中で子どもが示す「なぜ?」を大切にする
- 答えを教えるのではなく、一緒に調べる環境を作る
- 子どもが没頭できる時間と空間を確保する
プロジェクト型の探究
- 旅行計画を子どもに任せる(行き先の選択理由、交通手段、予算など)
- 家族の買い物計画を一緒に立てる
- 地域の身近な疑問を調べる(なぜこの場所に神社があるのか、など)
たとえば、以前からテニスに興味がある長男(小6)は、ある日「なぜあの選手はサーブのスピードがそれほど速くないのに、サーブの成功率が高いんだろう?」という疑問を持ちました。
彼は自分で選手のデータを調べ、角度や回転、コースなどの要素を考慮して、2時間ほど一人で部屋にこもって計算し、自分なりの仮説を紙にまとめていました。
論理に穴があるでしょうが、重要なのは「自分で問いを立て、調べ、考え、まとめる」という一連のプロセスを、誰に言われることもなく自発的に行ったこと。
地域の調べ学習イベントや科学館でのワークショップなども、家庭での探究活動を広げる良い機会になります。
もちろん、すべての疑問が深い探究につながるわけではありません。
興味が続かない場合は無理に続けず、別の機会を待つことも大切です。
2. IBの「CAS」的体験を家庭で作る方法
CAS(創造性・活動・奉仕)とは、体験を通じた学び、社会貢献への意識、バランスの取れた人格形成を目指す、IBの必修要素です。
教室での学習だけでは得られない、実体験を通じた成長を重視しています。
家庭でできる具体的な実践方法
CASの本質は「多様な体験を通じたバランスの取れた成長」だと思います。
特別な活動や高額なプログラムでなくても、日常の中で「作る」「動く」「貢献する」体験を意識的に取り入れることで、同様の効果を得ることができます。
子どもが「やらされている」と感じるのではなく、自分なりの楽しさや意味を見つけられるよう工夫することを、私は大事にしたいです。
子どもの興味を観察し、環境を整える
CAS的体験の出発点は、子どもが自然に示す興味や関心を丁寧に観察することです。
親の役割は、その興味を伸ばせる環境を整えることであり、特定の活動を強制することではありません。
- 「やらせたい」ではなく「やりたがっている」を重視する
- 既存の興味を組み合わせる機会を探す
- 試せる環境を提供し、結果は子どもに委ねる
以前、テニスと工作という長男の既存の興味を組み合わせて、ガット張りに挑戦させたことがあります。
一回で嫌になるかもしれないと覚悟していましたが、見事にハマり、半年もしないうちにクラブメンバーから受注を受けるまでになりました。
継続的な活動を通じた成長を重視する
一時的な体験よりも、継続的な取り組みを通じて得られる成長を大切にします。
これは必ずしも習い事である必要はなく、日常の中での継続的な関わりも含まれます。
- 結果よりもプロセスを重視する
- 長期的な視点で成長を見守る
- 一時的な停滞も受け入れる
次男(小4)は保育園の頃から建築中の戸建てに興味を示し、マインクラフトでの住宅作り、図書館での関連書籍、住宅展示場の観察など、場面は変わっても一貫した興味を確認しています。
この興味が将来どんな形になるかはわかりませんし、わからなくていいと思っています。
家族での役割を通じて社会性を育む
子どもが一番最初に遭遇する「社会」は家族です。
家庭内での役割を通じて、「独りよがりではないコミュニティの一員」としての自覚が自然と育まれます。
- 子どもを「お手伝い」ではなく「住人の一人」として位置づける
- 年齢に応じた継続的な役割を設定する
- 子ども自身が「家族の役に立っている」という実感を重視する
深い没頭体験を支える
子どもが何かに深く「ハマる」時間を確保し、尊重することです。
没頭体験を通じて育まれる集中力、持続力、探究する姿勢は、将来どのような分野に進んでも活かされる基礎的な能力となります。
- 集中できる時間と空間を確保する
- 途中で中断させない
- 完璧さよりも探究プロセスを重視する
3. IBの多面的評価を家庭で再現する方法
IBでは、テスト一発勝負ではない継続的な評価を重視し、論文、発表、実技、ディスカッションなど多様な表現方法で子どもの成長を見ます。
これにより、子どもの多様な能力や成長の過程を適切に評価できるという思想です。
家庭でできる具体的な実践方法
多面的評価の本質は「子どもの多様な能力を認める」ことですが、
家庭・保護者にできることは、その能力を見つけ出す執念を持つことだと思います。
学校のテストの点数だけでなく、子どもの思考力、表現力、協調性、継続力など、様々な側面から成長を見ることで、子ども自身の自己肯定感も高まります。
親が常にアンテナを立てて、子どもごとの活躍どころを用意する意識も、ときには必要です。
重要なのは、兄弟や他の子どもと比較するのではなく、その子なりの輝ける場面を見つけ出し、それを大切に育てることです。
子どもの活躍どころを執念深く探す
- 日常の小さな得意分野に気づくアンテナを立てる
- 子どもが自然と力を発揮する場面を記録する
- 「この子はここで輝いている」という瞬間を見逃さない
- 一つの分野にとらわれず、多角的に観察する
個別最適化された評価環境の構築
- 子どもそれぞれに合った評価方法を見つける
- 兄弟でも異なるアプローチを採用する
- 見つけた強みを伸ばせる機会を意識的に作る
- その子が「得意」を実感できる場面を増やす
成長の記録と振り返り
- 子どもの取り組みや成長の過程を写真や文章で記録する
- 定期的に子ども自身が振り返りできる機会を作る
- 成長の軌跡を可視化して自信につなげる
私も、兄弟それぞれの活躍どころを見つけるアンテナを常に立てています。
「平等」が基本とは思いつつも、それぞれが輝ける場所を見つけ出し、そこで力を発揮できる環境を整えることが「公平」だと考えています。
この執念を持って子どもを観察することで、思いがけない才能や興味の芽を発見することができると思います。
4. 国際的視野を家庭で育てる方法
IBは、多様な文化や価値観への理解、グローバルな課題への関心、異なる視点から物事を考える柔軟性を育成します。
これは単なる語学力ではなく、世界の多様性を受け入れ、自分とは異なる考え方を理解しようとする姿勢を指します。
家庭でできる具体的な実践方法
国際的視野の本質は「異なる視点を一旦でいいから受け止められる心の広さ」だと思います。
海外旅行や高額な語学教育がなくても、日常の中で様々な文化や価値観に触れる機会を作ることで、子どもの視野を広げることができます。
大切なのは、「正解は一つではない」「いろいろな考え方がある」ということを、具体的な体験を通じて理解してもらうことです。
多様な文化に触れる機会
- 世界各国の本や映画を楽しむ
- 異なる文化背景を持つ作家の作品を読む
- 地域の国際交流イベントに参加する
グローバルな視点での会話
- 世界で起きていることについて家族で話し合う
- 身近な出来事でも「なぜそうなったのか」「他の国ではどうなのか」という視点で考える
- ニュースを多角的に見る習慣を作る
言語学習の工夫
- アプリを活用した無理のない語学学習
- オンライン国際交流プログラムへの参加
- 地域の外国人との交流機会を見つける
たとえば図書館で世界各国の民話を借りたり、異なる文化背景を持つ作家の作品を選んだりすることで、「正解は一つではない」「いろいろな考え方がある」ことへの理解を自然に深められます。
わかりやすく国際的な体験でなくても、「こんな考え方もあるんだ」という小さな気づきの積み重ねが大切だと感じています。
学校の国際交流プログラムや地域の交流イベントなども活用できます。
ほかにも、地域の図書館や公民館で開催されるイベントなども、視野を広げる良い機会になります。
何から始める?家庭での実践ロードマップ
IBのような教育を家庭で実現しようとするのは、数ある選択肢の一つです。
学校や特別な教育環境にはそれぞれ独自の価値があり、家庭では得られない出会いや刺激、専門的な指導があることは否定できません。
ただし、高額な投資や特別な環境がなくても、家庭の工夫でできることもたくさんあります。
子どもの自然な興味を見逃さず、それを深められる環境を整える。
そして何より、子ども自身のペースを信頼する。
これらは、どの教育環境を選んでも大切な要素です。
以下、家庭でできる段階的なアプローチをまとめました。
学校や他の教育機会と組み合わせながら、それぞれのご家庭に合った方法を見つけていただければと思います。
今日からできること
最も手軽に始められるのは、日常会話での工夫です。
特別な準備は必要ありません。
「なんでなんだろうね?」を意識的に使い、子どもの意見を最後まで聞く習慣を作りましょう。
「正解」を求めるのではなく、考える過程を大切にすることがポイントです。
年齢に応じた家庭内での責任を与えることも、今日から始められます。
完璧を求めず、継続できそうなことからスモールステップを重ねることで、子どもの自立心と責任感を育てることができます。
1ヶ月以内に始められること
少し準備時間をかけて、IB的な学びの環境を整えていきましょう。
図書館の活用システム作り
地域の図書館が提供するプログラムを調べ、子どもの興味に合わせた本を一緒に選ぶ習慣を作りましょう。調べ学習の基盤となるスキルが自然と身につきます。
発表の機会作り
家族での発表会を定期的に開催し、子どもが体験したことを話してもらう時間を作ります。聞く側も質問やコメントをする習慣を作ることで、コミュニケーション能力の向上につながります。
長期的に取り組むこと
継続的な成長を支える環境を、時間をかけて構築していきます。
地域との連携強化
地域のボランティア活動を探し、子どもが興味を持てそうな活動を見つけます。継続的な社会貢献の機会を作ることで、奉仕の精神を育むことができます。
国際交流の機会拡大
オンライン国際交流プログラムを探したり、地域の国際交流イベントに参加したりして、多様な文化に触れる機会を増やしていきます。
年齢別のアプローチ
子どもの発達段階に応じて、重点を置く取り組みを調整しましょう。
小学生低学年
この時期は、日常会話での「なぜ?」の習慣化と基本的な生活習慣の確立が中心になります。読み聞かせや読書を通じて多様な世界観に触れることもできます。無理をせず、楽しみながら取り組むことがポイントです。
小学生高学年
図書館での調べ学習を本格化し、家族プロジェクトへの参加を促します。地域活動への参加も始められる時期です。子ども自身の興味関心を大切にしながら、活動の幅を広げていきましょう。
中高生
中高生になってからIBに関心を持ったとしても、家庭でできる探究型学習や国際的視野の育成は十分に意味があります。
より複雑な探究活動への挑戦や、国際交流プログラムへの参加が可能になります。自分なりの価値観の形成をサポートし、子どもの主体性を尊重することが重要です。
IBを選ばなくても、理想の教育は家庭で実現できる
IBのような教育を家庭で実現するための3つの原則があります。
第一に「子ども主体の学び」で、興味関心を起点とすること。
第二に「プロセス重視」で、結果よりも考える過程を大切にすること。
第三に「多面的な成長」で、一つの指標にとらわれないこと。
これらの原則は、どの家庭でも、どの教育環境でも応用可能です。
具体的な方法は、それぞれの状況に応じて工夫していけばいいんです。
小学生でも中高生でも、遅すぎることはありません。
子どもの成長に合わせて、その時々にできることから始めていけばいいんです。
「地方だから」「お金がないから」「選択肢がないから」と諦める必要はありません。
学校は確かに重要な教育の場ですが、万能ではありません。
家庭、地域、オンラインリソースなど、様々な「道具」を組み合わせることで、より豊かな学びの環境を作ることができます。
また、子育てには不確定要素がたくさんあります。
だからこそ変更ありきで、柔軟でいられるような仕組みが重要だと私は思います。
IBという特定のプログラムに固執するのではなく、子どもの成長に合わせて教育方法を調整していく柔軟性こそが、家庭教育の強みです。
必ずしも最初からすべてがうまくいくわけではありません。
失敗ありきで、それぞれのご家庭に合った方法を見つけて、子どもとの貴重な時間を楽しんでください。