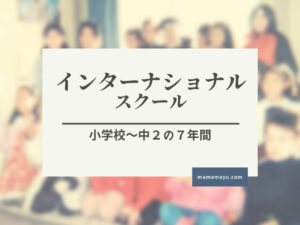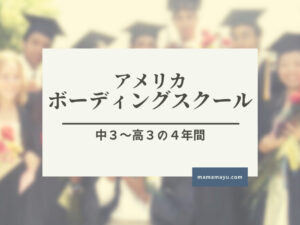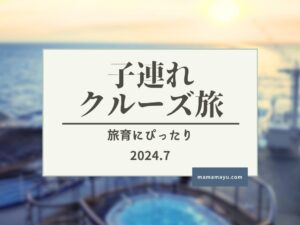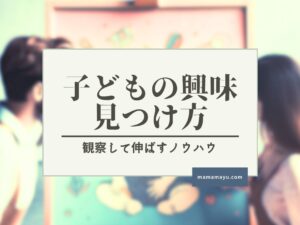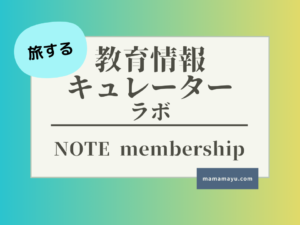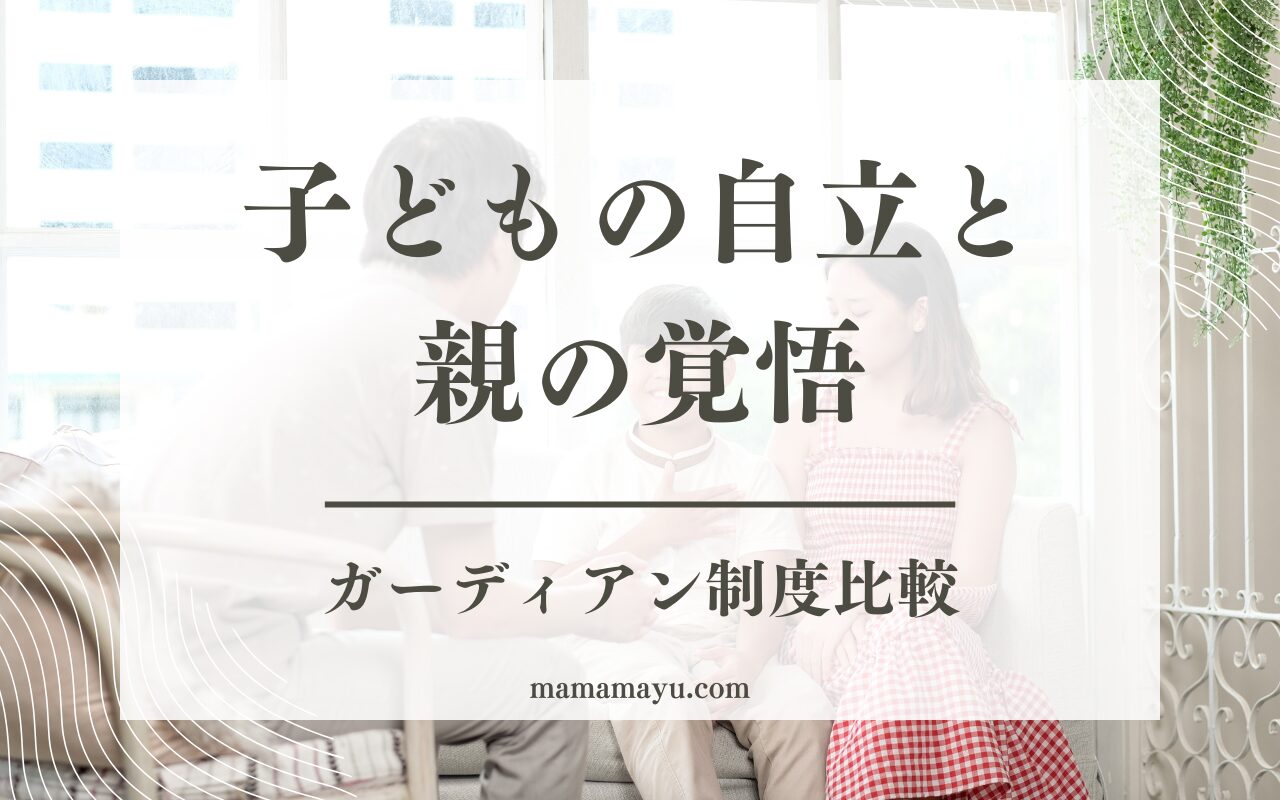以前、ニュージーランドの中高留学専門エージェントの方と意見交換したときのこと。
最近の中高留学生は、
「留学中も親子がつながりっぱなし」
「もはや親も半分留学している状態」
という話が印象に残りました。
私も親ですから「子どものことを全力で応援したいからこそ、動向をできるだけ把握したい」という親の気持ちも痛いほどわかります。
子どものことがわからなくなる「不安」もよくわかります。
でも親が「子どもの一番近い理解者」であり続けたいと強く思えば思うほど、子どもの自立や親離れを難しくするリスクもあるとも感じています。
そしてもうひとつ大事な観点として、子どもは多様な価値観や背景を持つ大人や仲間と関わることで、より柔軟で豊かな人間に成長できると私は思います。
親以外のさまざまな他者と接点を持つ体験こそ、留学の醍醐味であり、その人の成長の予後にも良い影響を与えるはずです。
単身留学中の中高生と親の距離感
私が留学していた2000年代は、まだ親との連絡手段も限られていました。
思い出したときにパソコンからメールするか、コレクトコールで電話するくらい。
親からはたまに小包や手紙、慣れないパソコンメールが届くくらいです。
スカイプとかもありましたけど、まだスマホもない時代に親が気軽に使えるものではありませんでした。
でもそのおかげもあり、日本にいる親とは自然と距離が保たれていました。
しかし、今はスマホ、SNSやLINEの普及によって、距離をほぼゼロにできてしまう時代です。
現在地アプリでピンポイントにどこにいるかわかるし、
直接つながらなくても、SNS経由で子どもの動向を嗅ぎ回る「保護者探偵」にもなれてしまいます。
親として「見守りたい」「不安」という気持ちは自然なものです。
でも、子どもの成長には親以外の多様な大人や第三者とかかわる経験も欠かせません。
そこで実際、単身留学中の中高生を誰がどのように支えてくれるのか2大系統の仕組みの違いを整理します。
中高留学の現地サポート・ガーディアン制度を比較
子どもを単身で留学させる保護者にとって最大の関心事は「現地では誰が子どもを見守ってくれるのか」「どんな仕組みなら安心して託せるのか」ということだと思います。
ここでは、中高留学先で「誰が親代わりを担うか」「どんなサポート体制が実際にあるのか」をざっくり国や地域ごとの仕組みの違いとして整理してみます。
※以下はおおまかな全体傾向です。学校・地域・プログラムごとに例外や変化も多いため、思い込みや決めつけを避け、最終的には必ずご自身できちんと確認することをおすすめします。
アメリカやスイスに多い「学校ワンストップ型」
「学校ワンストップ型」では、学校が生活全般を一手に引き受けるため、保護者的なケアから学習・健康管理、日々の困りごと対応まで、全て学校内で完結するケースが多いです。
生徒一人ひとりに対し、寮監や教員・アドバイザー・コーチ・医療スタッフなどがチームで見守る体制になっていることが多く、保護者とのやりとりも基本的に学校が一括対応してくれます。
このため、日本の親が現地で直接何かを手配する手間が少なく、「全部学校に任せられる安心感」「窓口が明快」「緊急時の対応も学校が主導で動いてくれる」という点が最大のメリットです。
その一方で、学校主導の生活になる分、学校内コミュニティ中心の交友関係や体験に限定されやすい傾向もあり、外部のローカル社会や市民と触れ合う機会はやや少なめになる人もいます。
もし学校との相性が良くない場合や、個別の価値観・スタンスにすれ違いが出た場合も、「相談先=学校内部」がメインとなるため、外部の目や第三者的な相談役が少ないという側面も知っておきたいポイントです。
現地校との保護者面談や日常のやりとりは、英語で行われるのが基本です。
「自分の英語に不安がある」「もっと保護者としてコミュニケーションを円滑にしたい」という方向けの記事も書いています。
イギリス・カナダ・オーストラリア・ニュージーランドに多い「外部ガーディアン/エージェント型」
「外部ガーディアン/エージェント型」では、学校とは別に、現地で信頼できる大人(ガーディアンやエージェントなど)を事前に定めることが国や州の法律として義務付けられています。
この大人が、生活面や緊急時のサポート、定期面談、病気・事故などの際の付き添い、各種手続き代行など幅広い役割を担うことも多く、一定頻度で本人と会いながら親へのレポートもしてくれるのが標準です。
最大の特徴は、学校外にも「親代わり」となる現地の大人がいることで、
- 学校でトラブルが起きたときの第三者的な相談窓口になる
- 地元コミュニティや家庭的な雰囲気の中で、より多様な価値観・人間関係に触れやすい
- 親が英語や現地文化に不慣れでも、日本語や多言語サポートを受けられるケースもある
などのメリットがあります。
一方、ガーディアンやエージェントは「人により当たり外れがある」「サポート対応や関与度に差が出やすい」「追加コストが発生する」などの注意点もあります。
現地でのつながりが広がる分、親としても自分でリサーチして信頼できる人物/業者かをじっくり見極める必要があります。
ローカルのガーディアンやエージェントを利用するときは、英語でやりとりするのが基本です。
「自分の英語に不安がある」「もっと保護者としてコミュニケーションを円滑にしたい」という方向けの記事も書いています。
マレーシアやタイも準ずる
マレーシアやタイのボーディングスクールでは、イギリス等のように「国としてガーディアン設置を義務とする」制度にはなっていません。
しかし実際には、学校が独自の方針で「ガーディアン」の登録や提携サービスの利用を求める運用が主流と見受けています。
一律の制度ではないので、事前に学校ごとに「ガーディアン制度の有無・要件・登録方法」を確認しましょう。
※以上はざっくりとした全体傾向です。学校・地域・プログラムごとに例外や変化も多いため、思い込みや決めつけを避け、最終的には必ずご自身できちんと確認することをおすすめします。
こうしてサポート体制を比べてみると、一見どれがベストか迷いがちですが、実際には家庭や本人の性格、価値観、優先順位、そのときどきのご縁によって合うスタイルは異なります。
要は、「どの国・制度が一番良い」かという話だけではないということ。
大切なのは、親が「子どもに一番近い理解者」ポジションから徐々に手を放し、信頼できる親代わりの大人を一人でも多く確保していくことだと私は考えています。
「子どもの自立=親離れ」だけでなく、親自身も「手放す覚悟」をもつ。
そして子どもにとっては、信頼できる大人との関係作りを学ぶきっかけになるのが留学です。
中高留学の親の不安を減らし、子どもの伸びしろを最大化する
現代は情報ツールのおかげで、親子のつながりを密に築ける時代です。
「留学中も親子がつながりっぱなし」
「もはや親も半分留学している状態」
が可能な時代とも言えます。
しかし子どもの伸びしろを最大化するためには「多様な大人との関わり」や「信頼して託すこと」も、意識しておきたいと私は思います。
「親の不安」を解消するには、サポート体制の違いをきちんと知った上で、自分たち家族に合った仕組み・信頼できる現地の大人(学校やガーディアン、エージェント)に託す覚悟が必要なのだと、改めて感じています。
現地の学校やサポート機関とのやりとりには「親の英語力や異文化対応力」が頼りになる場面が少なくありません。
「どんなオンライン英会話が、保護者向けに役立つの?」と感じた方にはこの記事で私のおすすめを紹介しています。