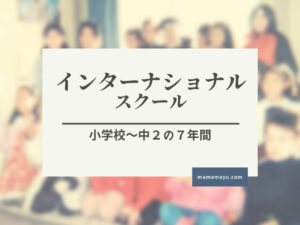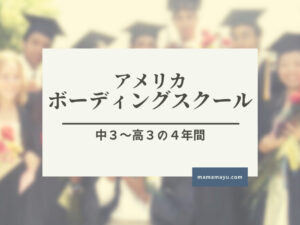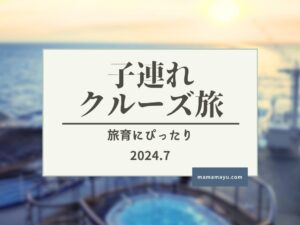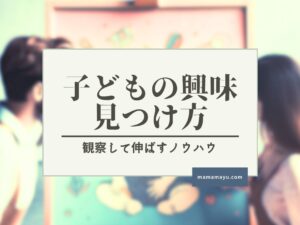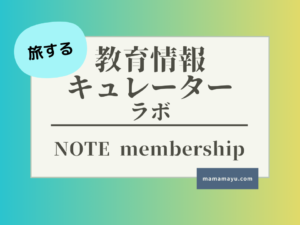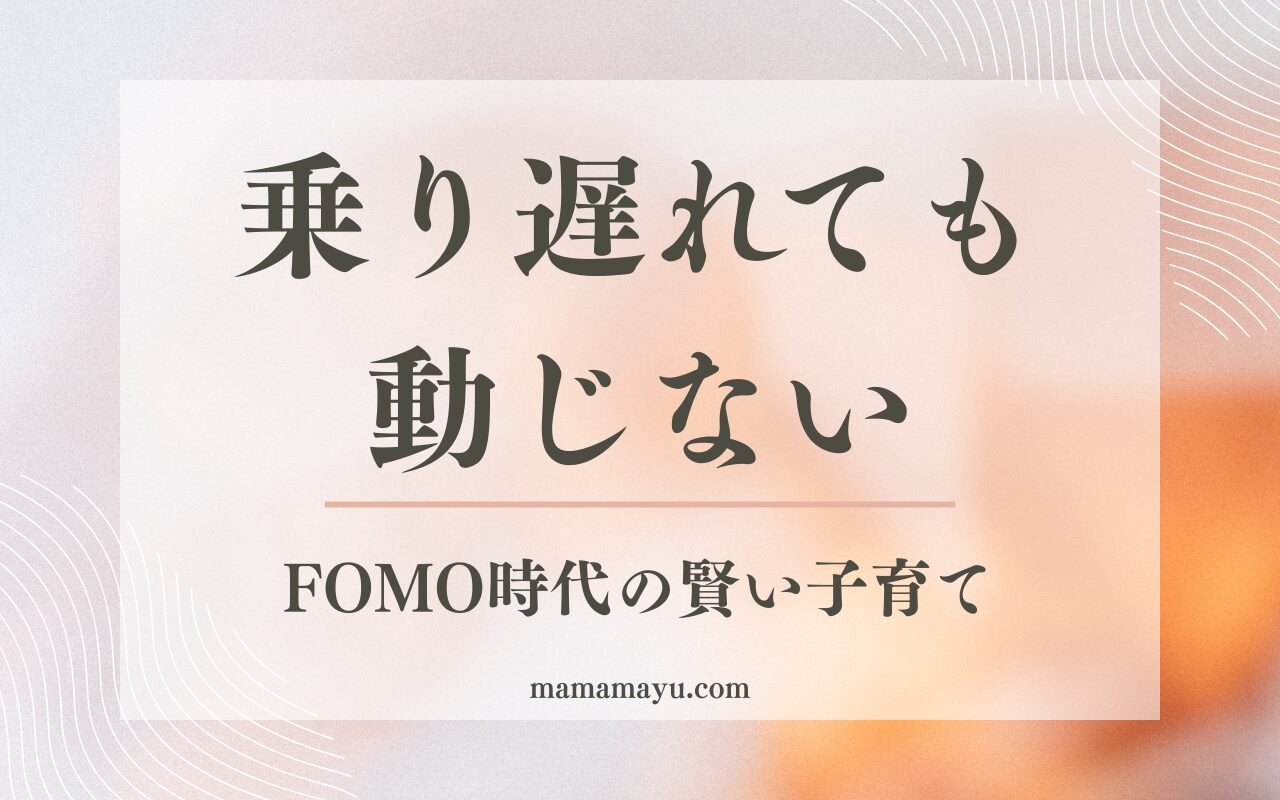「英語を習わせないと将来困る」
「プログラミングができないと時代に取り残される」
「あの学校に行かないと良い大学に入れない」…。
子育てをしていると、こんな不安に駆られることはありませんか?
SNSで他の家庭の教育方針を見て、うちも何かしなければと焦ったり、話題のイベントに行っておいたほうがいいと感じたり。
でも、本当に全部追いかける必要があるのでしょうか。
小6と小4の息子を持つ母として、また、普段の仕事柄、保護者の方々がこの「乗り遅れることへの恐れ」に悩んでいる姿を見かけます。
今回は、話題の万博を例に、FOMO(Fear of Missing Out)に振り回されない生き方について考えてみたいと思います。
FOMOとは?現代社会に蔓延する「乗り遅れることへの恐れ」
「○○ちゃんは英検3級に合格したんですって」
「△△くんはプログラミング教室に通い始めたそうよ」
「□□さんのお宅は夏休みにシンガポール旅行に行かれるとか」
こんな会話を聞いていると、だんだん心がざわざわしてきませんか?
「うちの子は大丈夫?」「何かさせなければ」「遅れているのでは?」
この感情こそが、FOMO(Fear of Missing Out)=「乗り遅れることへの恐れ」です。
FOMOが生まれる背景
なぜ私たちはこんなにも「乗り遅れる」ことを恐れるようになったのでしょうか。
情報があふれすぎている時代
スマホを開けば、世界中のニュースが瞬時に手に入ります。
友人のSNS投稿、教育情報、子育てのコツ、習い事の体験談…。
便利な反面、「知らなかったこと」「やっていなかったこと」がどんどん見えてしまうんですよね。
「あ、この情報知らなかった」「うちはこれやってない」という瞬間が、一日に何度も訪れます。
比較する機会が増えすぎた
昔なら、比較対象は近所の人や同級生くらいでした。
でも今は違います。
SNSを通じて、全国・全世界の「すごい子育て」「充実した家族時間」「教育熱心な家庭」の様子が、リアルタイムで目に飛び込んできます。
「○○ちゃんのお母さん、また素敵な投稿してる」
「あの家庭、また海外旅行?」
「△△の発表会、うちの子も参加させるべき?」
こんな風に、つい他の家庭と比べてしまう機会が圧倒的に増えているんです。
教育・子育ての「正解探し」が激化
「英語は早い方がいい」「プログラミングは必須」「中学受験しないと将来が…」
こうした情報が毎日のように流れてきます。
どれも「やらないと後悔する」「今しかない」という切迫感を伴っているから、つい焦ってしまいますよね。
でも、冷静に考えてみてください。
すべてを同時にやることなんて、時間的にも金銭的にも現実的ではありません。
何かを選ぶということは、何かを手放すということ。
それは当たり前のことなのに、なぜか「あれもこれもできていない」「全部やらなきゃ」と焦ってしまう。
これがFOMOの正体なんです。
子育てにおけるFOMOとの上手な付き合い方
ただ、FOMOは決して「悪いもの」ではないと、私は思っています。
むしろ、子育てにおいては自然な感情の一つです。
しかし、その感情が子どもに与える影響も無視できません。
「あれもこれもやらせなきゃ」と思いすぎると、子どもも忙しくなりすぎることがあります。
スケジュールに追われて、子どもが「やらされている感」を持ってしまったり、親子ともに疲れ果ててしまったり。
また、子どもは親の様子をよく見ています。
親が常に「他の子と比較して焦っている」姿を見ると、子ども自身も「自分は大丈夫かな?」と不安になることがあります。
それでも、FOMOすべてが悪いわけではない
我が家でも、長男が『仲いい友達がやっているから』、次男が『お兄ちゃんがやっているから』という理由で空手を始めたことがありました。
その時は、子どもたちの気持ちを優先し、詳しく分析する前にまず体験させてみようと考えていました。
結果的に、息子たちは空手に出会うことができたわけです。
私も夫も未経験の分野。
こういうきっかけでもなければ、子どもたちが経験することはなかったでしょう。
FOMOとの上手な付き合い方とは
つまり、FOMOを完全に否定する必要はないということです。
大切なのは、その感情に振り回されるのではなく、子どもの様子を観察しながら柔軟に対応すること。
合わないと感じたら方向転換する。
子どもが楽しんでいるなら続ける。
親が疲れすぎているなら一度立ち止まる。
完璧な判断を求めるのではなく、その時々で最善だと思える選択をしていけばいいのです。
万博を例に考える「話題の案件」に対する判断プロセス
今年話題の万博を例に、FOMOとどう向き合うかを考えてみましょう。
万博は確かに貴重な体験ができる場所です。
最新技術に触れたり、世界各国の文化を学んだり、家族で共通の思い出を作ったりできる素晴らしいイベントですよね。
でも、私は子連れで万博に行くつもりがありませんでした。
なぜでしょうか?
「話題の案件」に対する判断プロセス
万博のような大きなイベントや話題の習い事、進学先選びなど、要するに「みんなが注目している案件」に直面したとき、どう判断すればよいでしょうか。
我が家では、以下のような3つの質問で考えるようにしています。
質問1:なぜ多くの人がそれを選ぶのか?
- メディアで話題になっているから?
- 周りの人がやっているから?
- 将来への不安を解消したいから?
- 子どもに良い体験をさせたいから?
最新技術への興味、家族の思い出作り、社会参加の機会など、様々な理由で注目されています。これらの理由を整理すると、自分にとって重要なものとそうでないものが見えてきます。
質問2:本当に自分にとって価値があるのか?
- 時間的価値:この時間を他に使ったらどうか?
- 金銭的価値:この予算で他に何ができるか?
- 学習価値:子どもの成長に直結するか?
- 体験価値:代替できない唯一の体験か?
開催期間は長期間ですが、猛暑と混雑が予想されます。特に暑さ・混雑・新しい場所への不安傾向が高い小6と小4の息子たちにとって、これらの環境が本当に良い体験になるのかを考えました。
質問3:限られた時間とエネルギーをどう使いたいか?
- 子どもの興味・関心を深める時間
- 家族でゆっくり過ごす時間
- 新しいスキルを学ぶ時間
- 地域コミュニティとの関わり
同じ予算で家族それぞれのペースで楽しめる旅行、個別の科学館見学、オンライン体験など、他の選択肢と比較検討しました。
私と夫の間では、万博は「行かない」という結論になりましたが、最終的には親戚が子どもたちを連れて行ってくれることになりました。
結局、上のような判断プロセスを踏んでも、現実はもっと複雑です(笑)
家族の中でも価値観が違うこともありますし、それはそれで自然なことだと思っています。
明確な答えが見つからなくても大丈夫です。その通りに行かなくても大丈夫。
「やらない」選択と「それでもやる」選択、どちらも価値がある
私自身は子どもたちと万博に行かないという結論に至りました。
行くか行かないか、そのどちらの結論も意味があると思っています。
「やらない」選択
「やらない」ことで、時間や経済的な余裕が生まれます。
子どもが自分のペースで成長でき、その子らしさを大切にできる。
比較や競争から解放されて、家族で過ごす時間も増やせます。
「それでもやる」選択
一方で、「みんながやっているから」「話題だから」やる場合も、立派な参加理由になります。
「そんな理由で選んではいけない」と言われがちですが、それも一種の思い込みです。
共通の話題を通じた社会とのつながり、予想外の学びや出会い、家族の思い出作り、子どもの社会性を育む機会…。
なにかしら得られることがあります。
FOMOに振り回されない生き方を考える上で、忘れてはいけない大切な視点です。
自分らしい選択をする力を育てる
FOMOに振り回されない生き方とは、自分の選択を大切にしながら、他者の選択も尊重することだと思います。
万博に行く人も行かない人も、英語を学ぶ子もそうでない子も、留学する子もしない子も、それぞれに意味のある道を歩んでいます。
大切なのは、「人それぞれに理由があっても(なくても)いい」と理解することです。
教育や子育てにおいて、画一的な正解はありません。
子どもたち一人ひとりの個性や興味、能力に合わせて、最適な環境や機会を見つけていくことが私たちの役割だと考えています。
FOMOは現代社会に生きる私たちにとって避けられない現象かもしれません。
でも、それに振り回されるのではなく、自分らしい選択をする力と、多様な選択肢を認め合う力を身につける。
そうすることで、より納得できる人生を送れるのではないでしょうか。
完璧な判断をする必要はありません。
時には失敗もあるでしょう。
でも、選択を重ねる経験がなくては、必要な力も育ちません。
あなたも、FOMOに振り回されることなく、自分らしい選択をしてみませんか?
そして、子どもや他の人の選択についても、温かく見守ってみませんか?