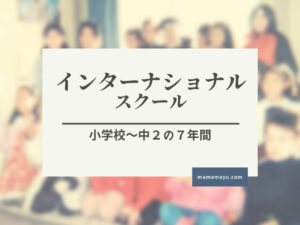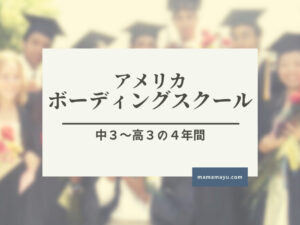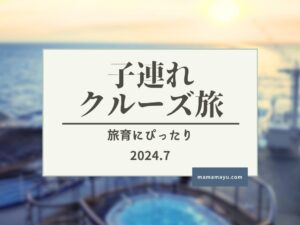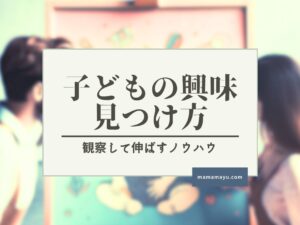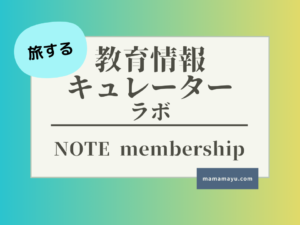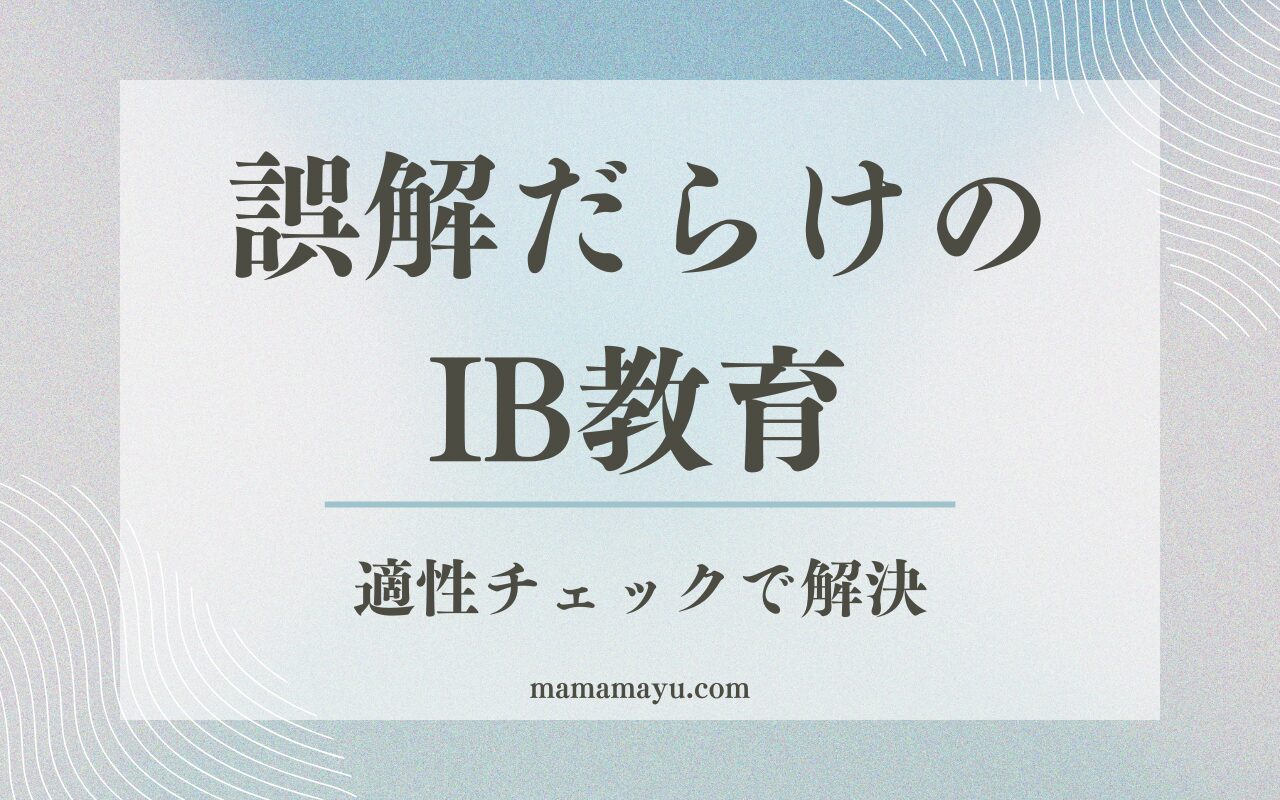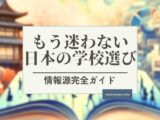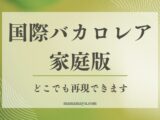教育について調べていて、『国際バカロレア』(International Baccalaureate、略してIB)という言葉を目にしたことはありませんか?
周りで話題になっているけれど、本当にうちの子に必要なのか迷っていませんか?
私も小6と小4の息子を持つ現役保護者として、この気持ちはよく分かります。
「国際的」「インターナショナル」という魅力的なイメージに心が動く一方で、
「本当に良いものなのか」「うちの子に合うのか」「続けられるのか」という様々な不安と期待が入り混じる複雑な心境。
断片的な情報に振り回されて、結局何が正しいのか分からなくなってしまう。
そんな経験をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
私は、インターナショナルスクールやアメリカのボーディングスクールでの経験、そして東京大学教育学部での学びを経て、現在は教育コンサルタントとして活動しています。
IBに特化しているわけではありませんが、だからこそ保護者目線で冷静に分析し、誤解を解いて適切な判断をするための具体的な方法をお伝えできると考えています。
この記事を読むことで、IBに関する正しい基礎知識を身につけ、わが子に最適な教育選択ができるようになることを願っています。
国際バカロレア(IB)について最低限知っておきたいこと
まず、IBについて正しく理解するために、基本的な定義を整理しましょう。
断片的な情報に惑わされないためには、正確な基礎知識が不可欠です。
国際バカロレア(IB)とは何か
IBとは、International Baccalaureate(インターナショナル・バカロレア)の略で、スイスに本部を置く国際バカロレア機構(IBO)が提供する国際的な教育プログラムです。
世界共通のカリキュラムと評価基準を持ち、現在世界約160の国と地域で実施されています。
国際バカロレア(IB)の4つの年齢別プログラム
IBには年齢に応じた4つのプログラムがあります。
- PYP(Primary Years Programme):3-12歳対象の初等教育プログラム(年少~小5)
- MYP(Middle Years Programme):11-16歳対象の中等教育プログラム(小6~高1)
- DP(Diploma Programme):16-19歳対象の高等教育プログラム(高2・高3)
- CP(Career-related Programme):16-19歳対象のキャリア関連プログラム(高2・高3)
「IB」が話題に上がっても、発信者によって指しているプログラムが異なる場合があります。
すべてのプログラムに共通する理念はあるものの、実用面では異なる部分が多いです。
情報を収集する際は、「PYPのこと?」「MYPのこと?」「DPのこと?」「それともIB全体のこと?」と、どの範囲について言及しているのかを確認しましょう。
国際バカロレア・ディプロマ・プログラム(DP)の基本構造
4つあるプログラムのなかでも特に関心度が高いとされる高校の「DP」は、こんな構造になっています。
- 6つの教科グループから1科目ずつ選択
- 言語と文学(母国語)、言語習得(外国語)、個人と社会、理科、数学、芸術の6分野から各1科目を選び、2年間履修
- 学習レベルの設定
- 6科目のうち3~4科目を上級レベル(HL)、残りを標準レベル(SL)で学ぶ
- 3つの必修コア
- TOK(知の理論)、CAS(創造性・活動・奉仕)、EE(課題論文)は全員必修
- 最終評価
- 国際バカロレア試験で45点満点中24点以上を取得することで、IBディプロマを取得
日本での国際バカロレア(IB)の状況
日本では現在、一条校(日本の学校教育法に基づく学校)とインターナショナルスクールの両方で、PYP、MYP、DPの国際バカロレア(IB)認定校が存在しています。
近年は「日本語DP」も増加しており、IB入試を実施する日本の大学も増えています。
CPについては、2025年3月に長野日本大学高等学校が日本初のCP認定校となったそうですが、まだ認知度は低く、今後の展開が注目されます。
保護者が陥りがちな7つの誤解
IBについて『国際的で素晴らしい教育』というイメージを持たれている方も多いと思います。
実際、IBには優れた面がたくさんあります。
でも誰しも最初に持った印象に引っ張られがちですよね。
念のため、一度フラットな目で見直してみませんか?
よくある誤解や先入観を整理しておくことで、より冷静な判断ができるはずです。
誤解1:国際バカロレアはインターナショナルスクールのこと
初期のIB導入校がインターに多かったために、この印象が定着したようですが、
IBは教育プログラムの名称で、学校の種類とは関係ありません。
公立や私立校でもIB認定校は存在し、逆にインターであってもIB認定を受けていない学校もあります。
誤解2:IBは英語でしか学べない
一部誤りで、一部正しいというのが現状です。
PYPとMYPの段階では、日本語中心の授業が行われているところも多いです。
一方、DPでは「日本語DP」が普及中であるものの、実態はDual Language Diploma Program(DLDP)。
つまり「日本語DP」は日英併用のプログラムとして、最低2科目は英語で実施することが義務付けられています。
つまりIBでは完全に英語必須ではありませんが、特にDP段階では一定の英語力が必要になるというのが実情です。
ついでに、日本語DPでの専門科目の選択肢は英語DPと比べると限定されがちで、英語の使用配分や科目の選択肢は学校によって大きく異なる点には注意です。
誤解3:IBは帰国子女や国際的な家庭の子ども向け
「国際」という言葉から特別な背景が必要だと思われるかもしれませんが、実際は、日本育ちの生徒も多数在籍しており、国際的な視野を育てたい日本の家庭にも適しています。
誤解4:IB以外では海外大学に行けない
IBの海外大学進学実績が注目されることで、IBが必須条件だと誤解されがちなのかもしれません。
一般的な日本の高校卒業資格でも海外大学受験は可能です。
SATやA-levelなど他の国際的な資格も有効で、IBは選択肢の一つに過ぎません。
誤解5:IBがあれば海外大学に確実に合格できる
DPを修了して、IBディプロマを取得しても自動的に大学の合格が保証されるわけではありません。
各大学には独自の選考基準があり、スコアだけでなくエッセイや課外活動や面接など、他の項目でも評価されます。
誤解6:IBは日本の大学受験に不利
保護者世代が経験してきた従来の受験システムとの違いから、不安を感じるのも無理はありません。
IB入試を実施する日本の大学は増えていて、しかも一般入試との併願も可能な場合が多いです。
むしろ入試の機会が増える可能性があります。
誤解7:IB=最先端=ベストな教育
IBは確かに優れた教育プログラムですが、子どもの学習スタイルや興味によって適性は大きく異なります。
「最新」や「国際的」が必ずしも「最適」ではありません。
冷静な選択のための考え方
IBに関する基本知識と誤解を整理したところで、次は冷静に判断するための具体的な考え方をお伝えします。
感情的な判断や周囲の意見に流されることなく、わが子にとって最適な選択をするためのフレームワークです。
判断の3つの軸
IBの適性を判断する際は、以下の3つの軸で総合的に評価するといいと思います。
まずは概要だけ。
1. 子どもの適性
学習スタイル、興味、能力などと、IBの整合性を確認します。
IBの学習方法が子どもの特性に合っているかどうかは、最も重要な要素です。


2. 進路目標との整合性
具体的な進路目標があるならば、IBの必要性を照らし合わせます。
なぜIBを選ぶのか、他の選択肢と比較してどのような優位性があるのかを明確にしましょう。


3. 家庭のリソース
経済的負担、時間的コミット、サポート体制を現実的に評価します。
無理のない範囲で継続できるかどうかが成功の鍵となります。

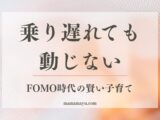
判断プロセス
以下の4つのステップで段階的に判断を進めることをお勧めします。
- Step 1現在の状況を整理する
子どもの現在の学習状況、興味関心、将来の希望などを把握
- Step 2チェックリストで適性を確認する
次で紹介するチェックリストを使って、IBへの適性を評価
- Step 3代替手段と比較検討する
IBの良い部分を他の方法で実現できないか、費用対効果を含めて検討
- Step 4家族で話し合い、決断する
収集した情報をもとに、家族全員で納得のいく決断を下す
決断のタイミング
IBを検討するなら、情報収集は早めに始めるに越したことはありません。
通学可能な学校は限られており、プログラムの質や雰囲気を見極めるために時間が必要だからです。
IBの設計的にはMYPからDPへの流れが理想的とされていますが、
DPのある学校でMYPがない場合も多く、DPからの参加も一般的です。
寮生活を考慮すれば選択肢は広がります。
IBDPへの参加には主に2つのパターンがあります:
パターン1:IB校に最初から入学
- 中学卒業後までにDPがあるIB認定校に入学
- 高1は準備期間、高2・3でDP履修
パターン2:高校途中でIBDPに参加
- 他校から高2に進級するタイミングでIBDPに転入
- 日本では少数派の選択肢ですが、IBDPの特性上、海外ではこのタイミングも一般的
どちらのパターンでも、中学3年生が始まる頃までには情報収集を開始し、英語力の準備も計画的に進める必要があります。
日本語DPでも英語が必要です。
一般的な高校カリキュラムはCEFR A2到達が目標ですが、
私の完全に独断の目安としてはDP開始時に最低でもB1はあってほしいです。
もちろん、その後も努力して英語を伸ばすつもりで。
普通の学校の中卒レベルはA1ですので、計画的に準備する必要があります。


うちの子にIB(国際バカロレア)は合う?向き不向きチェックリスト
ここでは、実際に子どもがIBに適しているかどうかを判断するための具体的なチェックリストをご紹介します。
すべての項目に当てはまる必要はありませんが、多くの項目で「はい」と答えられる場合は、IBへの適性が高いと考えられます。
学習スタイルの適性チェック
子どもの普段の学習の様子を思い浮かべながら、以下の項目をチェックしてみてください。
□ 継続的な努力と時間管理ができる
宿題や習い事を計画的に進められ、長期的な目標に向けて継続的に取り組める
□ プロセス重視の学習に取り組める
結果だけでなく、どのように考えたか、どのような過程を経たかを大切にできる
□ 多面的な評価に対応できる柔軟性がある
テスト以外の評価方法(発表、論文、実技など)にも前向きに取り組める
□ 探究型学習に興味を示す
「なぜ?」「どうして?」という疑問を持ち、自分で調べて考えることを楽しめる
目標との整合性チェック
IBを選択する目的と、子どもや家庭の目標が一致しているかを確認します。
□ 海外大学進学を具体的に考えている
単なる憧れではなく、具体的な進学計画や準備を進めている
□ 国際的な視野を育てたい明確な理由がある
なぜ国際的な視野が必要なのか、将来どのように活かしたいかが明確
□ 2年間のハードなカリキュラムに対応できる
IBDPの学習負荷を理解し、それに対応できる体力と精神力がある
家庭のリソースチェック
IBを継続するために必要な家庭のサポート体制を確認します。
□ 経済的な負担に無理がない
学費だけでなく、関連する費用も含めて家計に無理のない範囲である
□ 保護者のサポート体制が整っている
IBの理念を理解し、子どもの学習を適切にサポートできる環境がある
□ 長期的な視点で判断できる
短期的な成果を求めすぎず、子どもの成長を長期的に見守れる
見直しチェックポイント
以下の項目に多く当てはまる場合は、IBがオーバーキルになっている可能性があります。
□ 日本の大学のみが志望で国際環境を特に求めていない
国内進学が主目的で、IBの国際的な要素を活かす予定がない場合
□ 「国際的」というイメージを優先している
IBの本質的な教育内容よりも、「国際的」という響きに魅力を感じている場合
□ 子どもの適性より保護者の願望が先行している
お子さんの興味や能力よりも、保護者の期待や理想が判断基準になっている場合
我が家にとってのベストな選択を見つけるために
IBは確かに優れた教育プログラムですが、万能ではありません。
最も重要なのは、子どもの個性と家庭の価値観や状況に照らして、IBが本当に適した選択肢かどうかを冷静に判断することです。
「高価=良い教育」「国際的=最良」とは限りません。
完全無欠なサービスはなく、どの選択にも「穴」は残ります。
どんなに「良さげ」な学校や教育を選んでも、最終的に穴を埋める判断をする家庭の役割はなくなりません。
もしこの記事を読んで、「やっぱりIBいいかも!」と思ったならば、以下の行動をお勧めします:
- 実際のIB認定校の見学や説明会への参加
- 在校生や卒業生に話を聞く機会を設定
- 家族での継続的な話し合い
そして、もしIBの適性チェックを通じて「うちの子には合わないかも」と感じた方がいらっしゃっても、心配は無用です。
IBの魅力的な教育要素は、実は家庭や地域でも再現できると、私は考えています。
続きの記事にて、IBを選ばない場合でも、同様の教育効果を得るためのアプローチや考え方をご紹介します。